第八話 青年インカ(19)
やがて、ベルムデスとの話しを終え、どこか意識の飛んだような状態で、アンドレスは天幕の外へと出た。
外では、既に、夜明けを告げる山鳥の声が、遠く、甲高く、響いている。
今しがた、ベルムデスと過ごしたのは、ほんの数時間のはずなのに、めまぐるしく、長大な時が流れ去ったかのような感覚が、強い残光のように残っていた。
天幕の出口で立ち止まったまま、深呼吸なのか、溜息なのか、長く深い息がアンドレスの口元から漏れる。
辺りは、漆黒の闇の頃を過ぎ、透明な藍色がかった清涼な空気に満たされている。
ふと見上げる早朝の空には、明けの明星が白く清らかな光を放っていた。
気付けば、あれほど激しく吹き荒れていた雪も、今は、すっかりやんでいる。
(いつの間に、雪がやんでいたんだろう……)
美しい白銀の世界へと変わった大地の上で、降り積もった雪を踏みしめながら、アンドレスは朦朧としながらも、一歩、一歩、歩みはじめた。

時々、道で出会っては、「アンドレス様、お早いですね!」と、朗らかに礼を払って、早番の衛兵たちが過ぎていく。
そんな早朝から活動をはじめている兵たちの目を、今は、そっと逃れたい気持ちで、彼の足は自然に野営場のはずれに向いていた。
この先々の反乱の展開を思うと、まだ頭は激しい混乱の渦を巻くばかりだった。
(まさか…英国まで巻き込む方向に動いていただなんて…――!!)
深い息をつきながら見つめる空は、藍色から次第に透明な蒼色へと移り、徐々に白みが差してくる。
移りゆく空の景色の中で、明けの明星が、変らぬ清い光を放ち続けている。
その星を仰ぎ見るアンドレスの瞳から、一筋の涙が頬を伝って流れた。
(しかも…父上は暗殺……――)
これまでも、侵略者たちの非道な暴虐ぶりには、怒り心頭に発すること数知れず、彼の心は幾度となく憤怒の炎に燃え上がってきた。
だが、これほどに己の身近でも、その暴挙が行われていたとは―――!!
アンドレスは涙を流しながらも、強くその拳を握り締める。
今、彼は、はじめて、真にインカの民の舐めてきた苦汁を、己自身の血肉として、鮮明に理解することができる気がしていた。
アンドレスは、もう一度、天空を振り仰ぐ。
白みゆく空に溶けゆく、純白に輝く明けの明星……――見つめる彼の脳裏には、愛しいひとの姿が甦る。
(強制労働という名で両親の命を奪われた君の気持ちが、今、やっと本当に分かる気がする…コイユール……!!)
やがて彼の足は、知らず知らずのうちに、負傷兵たちの治療場界隈へと向いていた。
相変わらず、治療場では夜を徹して看護の女性たちが熱心に立ち働いていて、案の定、それらの女性たちに混ざって、コイユールの姿もあった。
アンドレスの先日の水攻め作戦では、街中での銃撃戦を伴う結果となり、それ故、負傷兵の数は再び増加していた。
それでも、献身的な従軍医たちの治療や、看護の女性たちの熱心な介抱により、それらの兵たちも、次第に快方に向かっているようだった。

そうした負傷兵たちに向けられるコイユールの柔和で繊細な眼差しも、静かに染み入るように嬉しそうに見える。
アンドレスは治療場外の木陰で足を止めると、熱く込み上げる胸を片手で押さえた。
(コイユール…――……!)
本当は、すぐにでも、コイユールの傍に駆け寄って、抱き締め、今の自分の気持ちの何もかもを話したい、聞いてほしい、そして、彼女自身の中に深く刻まれた心の傷つきの何もかもをも包みたい――そんな、強い衝動に駆り立てられる。
しかし、周囲は、朝の行動を開始した兵たちで次第に賑わいはじめており、アンドレスは、思いをぐっと堪(こら)えて足を止めた。
無意識に、彼の指先は、その胸元から光る小瓶を取り出していた。
小指サイズほどの、そのガラス瓶は、透明なオイルで満たされ、その中に、色彩美しい種子類や鉱石の欠片などが9種類ほど、ぎっしりと詰められている。
清々しい朝日を浴びてキラキラと眩い煌きを放つ小瓶――それは、コイユールが、彼のために作ってくれたグランデーロのお守りだった。

アンドレスは、暫し、手の平の中の優しい輝きを見つめた後、そっと、その小瓶に口づける。
そして、今一度、コイユールの姿を振り返ると、静かに踵を返した。
かくして、その頃、アンドレスが見上げていたのと同じ明けの明星を、遥か離れた山岳の秘都で見つめている人物がいた。
反乱の本拠地、ペルー副王領―――。
早朝のマチュピチュは、どこまでも白く立ち込める朝もやに、深く包まれている。
まさに天空都市の名そのままに、完全に空と雲霧の中に溶け込み、この地が最も神秘的な表情を見せる時間帯である。
白い濃霧の中に霞んで見え隠れする遺跡の石壁たちの間を、一人、朝露に濡れた石畳を歩みながら、トゥパク・アマルは、静かな眼差しで天空を見上げていた。
水滴を帯びて、しっとりと風に舞う絹糸のような長髪は、女性のそれのようでさえあるが、その表情は美麗でありながらも非常に精悍で、厳然としている。
古(いにしえ)のインカ帝国時代、神殿や家々の石壁は白亜に塗られていたという――そんな神々しく純白な輝きに満ちた聖都でありし時代を彷彿とさせる、白い朝霧に抱かれた早朝のマチュピチュ――……。
褐色の逞しく引き締まった長身に、まるで真綿がまとわりついてくるかのように濃密な朝もやは、一寸先の視界させ利かせてはくれぬが、対照的に、見上げる天頂は、実にすっきりと澄み渡っている。

夜の濃い群青色から柔らかな紫色へと移りゆく上空では、白く輝く星々が、ひとつひとつ光の中へと淡く溶けていく。
それらの星々の中で、ひときわ眩い煌きを放つ明けの明星を見つめながら、やがて、彼はゆっくりと足を止めた。
白い霧の向こうに、何者かの微かな気配がする。
トゥパク・アマルは変わらぬ静寂な佇まいのまま、意識だけを、すっと、そちらに向けた。
霧の向こうで、その気配の主が居住まいを正して跪き、深々と恭順を払う様子が窺える。
一呼吸あってから、トゥパク・アマルの低く囁く声が、朝もやを微かに震わせた。
「何か動きがあったか?」
(はい……トゥパク・アマル様……!)
濃密な霧の向こうで、草陰深く身を隠しているのだろうか、全く姿の見えぬその何者かが、深く礼を払う気配だけが返ってくる。
「そうか。
それで、如何なる様子か」
(はい…!
トゥパク・アマル様のご計画通り、事は動き出したもようでございます……!!)
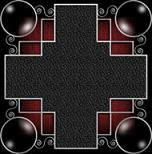
トゥパク・アマルは、切れ長の目を僅かに細めた。
その目元に、瞬間、閃光が走る。
それから、彼は、姿の見えぬ相手の、つまりは彼の放った斥候の一人なのだが、その声の主の方向に一歩、踏み出した。
「では、実際に動き出した可能性があるということか?」
(はい…!
ですが、畏れながら、陛下…なにぶん、海を隔てた遥か遠方での動きゆえ、正確に情報を掴むことは非常に難しいのです……)
「うむ。
それは、わたしも心得ている」
(畏れ多いことでございます!
トゥパク・アマル様……!)
斥候が非常に深く畏まり、地につくほどに身を低める気配が伝わってくる。
(ですが、陛下、この大陸全土の沿岸各地に散って情報収集に奔走している者たちには、海の向こうの動きさえも、微かに打ち寄せるさざ波をとらえるがごとく、敏感に、耳聡く、察知するに長けております者もおりますゆえ……!

沿岸部には海向こうの噂も流れ込みやすく、それに、スペイン人の貿易商と密かに通じている仲間たちもおりますゆえ、国外の情勢も、ちらほらと伝わって参ります。
しからば、此度の件も、あながち的は外れていないかと…!!)
トゥパク・アマルは研ぎ澄まされた厳然たる面差しで、姿の見えぬ相手の言葉に耳を傾けつつ、低く言う。
「いずれにしろ、よく調べてくれた。
今は、国際情勢を正確に把握することこそ重要だ。
容易な任務ではないが、引き続き、状況の推移を追ってくれるか」
(はっ!!
皇帝陛下……!!)
トゥパク・アマルが頷くと、声の主は朝もやの向こうで再び深く恭順の礼を払い、たちまち、その気配を消した。
相手の気配の遠ざかるのを確認すると、トゥパク・アマルは、やや下向き加減にしていた鋭利な横顔をゆっくりと上げる。
そして、次第に昇りくる太陽に向き直り、深く礼を払った。

今、トゥパク・アマルを照らし出すかのように、朝一番の陽光が、朝霧の中を貫いて真っ直ぐに彼の元へと差し込んでくる。
それと共に、朝霧を成していた細やかな水の粒子に陽光が煌いて反射し、辺り中が眩い黄金色の光を燦然と放ちはじめた。
天空都市マチュピチュ全体が、神聖な黄金色の炎に燃え上がる瞬間である―――。
やがて、こちらに歩み来るトゥパク・アマルを、やや離れた場所から護衛していたビルカパサが、丁寧に礼を払って迎える。
黄金色に輝く霧の中から、次第に姿を現す主(あるじ)の姿は、燃え上がる清冽な炎に包まれているかのようだ。
その姿は、どこか人間離れした、非常に厳粛な気配に満ちている。
ビルカパサは、息を詰め、そちらに釘づけられた。
「ビルカパサ、待たせてすまぬ。
陣営に戻ろう」
トゥパク・アマルの声に、ビルカパサはハッと我に返った。
「は、はい!!
トゥパク・アマル様!!」
彼は、冷風を切って歩みゆくトゥパク・アマルの後を、慌てて追っていく。

深い思慮に耽ったようにして、鋭い目で歩み進むトゥパク・アマルの斜め後方に従いながら、ビルカパサは主の横顔を俊敏に窺う。
常の精悍な面差しに、さらなる強い力と険しさを宿して、早足で歩むトゥパク・アマルの様子に、ビルカパサは事態の進展を悟った。
その気配に気付いてか、前方を見据えたまま、トゥパク・アマルが口を開く。
「どうやら動き出したようだ」
「そうでしたか……!」
ビルカパサの表情にも、強い緊張と共に光が射した。
そんなビルカパサを振り向いて、トゥパク・アマルは真摯な眼差しで相手を見つめる。
「いよいよだ。
ここを降りて下界に戻る準備に入らねばなならぬ。
まずは、インカ軍本隊をあずけているディエゴの軍と早急に連絡を図りたい」
ビルカパサは、すかさず、頷いた。
「はっ!!
トゥパク・アマル様!!」
マチュピチュの石畳を歩む二人の足取りにも、無意識のうちに、その一歩ごとに力が入っていく。
「ところで、あの地下道だが…――」
「え?」
不意のトゥパク・アマルの言葉に、ビルカパサは、瞬間、瞳を瞬かせた。
「あの地下道……わたしが、クスコの牢から脱出する際に利用した地下道だが、使えるかもしれぬ」
「使えると…?
戦にでございますか?!」
「うむ。
早急に地下道の状態を調べるよう、手配をしてもらいたい。
特に、次なる戦の要(かなめ)となろう地に通じる地下道――クスコ(Cuzco:インカ帝国の旧都)とリマ(Lima:スペイン側の中枢都市)の間、そして、クスコとアレキパ(Arequipa)との間に通じる地下道を。
いや、リマとアレキパとの間も、忘れてはならぬ。
長い間、放置されてきたゆえ、かなり老朽化はしていようが、あれほどの地下道を放置しておくのは、あまりに惜しい。
ある程度の整備をすれば、必ずや、有効な使い手があろう。
少々、わたしに考えもある……」

「クスコとリマの間、そして、クスコとアレキパの間――!
アレキパ…!!
沿岸に近い要衝の町でございますね?」
ビルカパサは、興奮に顔を紅潮させながら、噛み締めるように呟いた。
「そうだ――」
トゥパク・アマルが深く頷く。
「次なる戦の重要な舞台となるかもしれぬ沿岸にほど近い町―――」
低く決然としたトゥパク・アマルの声音に聴き入りながら、ビルカパサは、激しい緊迫感と武者震いが、電流のごとく己の全身を走るのを感じていた。

太陽の上昇に伴い、徐々に晴れゆくマチュピチュの朝霧……。
やがて霧がすっかり空気の中に溶け込むと、朝露に濡れた石畳に陽光が降り注ぎ、遺跡は神秘的な夜明けの光景から明るい午前のそれへと、その表情を変えていく。
トゥパク・アマルは前方を見据えていた鋭利な眼差しを、ゆっくりとビルカパサの方に戻した。
そして、その瞳の色を和らげ、僅かに微笑む。
「この秘都での生活も、間もなく終わりとなろう。
ここでの静かな日々と別れを告げるのは、少々、惜しくもあるが……」
ビルカパサはきっぱりと顔を上げて、凛々しい目で、真っ直ぐに主を見つめた。
そして、太く、逞しい声で力強く言う。
「トゥパク・アマル様!!
国中の民が、あなた様のお帰りを待ち侘びておりましょう!!」
とどまることなく昇りゆく太陽が、二人の歩みゆく石畳の道を、眩く照らし出していた。
他方、この頃、隣国ラ・プラタ副王領では、トゥパク・アマルの秘策による新たな大波到来の可能性を知ったアンドレスが、急ぎ、次なる戦地へと駒を進めようとしていた。

インカ軍にとって、ソラータ奪還は意義深いものであったとは言え、この反乱の全体的な戦況は、まだまだ彼らにとって厳しいものであることに変わりはなかった。
本格的な反乱の決着をつけるためには、ペルー副王領のスペイン軍本隊を押さえ込むことが、最終的には、絶対に避けて通れない。
だが、そのためにも、このラ・プラタ副王領でのインカ側の地盤を、しかと固める必要があった。
奪還したソラータに、街の守備と復興作業のための分隊を残すと、アンドレスは、トゥパク・アマルの書状で指示されていた通り、すぐさま、アパサが激戦を展開しているラ・パスへと進軍を開始した。
ソラータの水攻め成功の機運に乗り、このまま一気にラ・パスをもインカ軍の手に奪還し、一挙にラ・プラタ副王領でのインカ軍の勢力を確実なるものにしたい!!――それは、全てのインカの民の次なる願いでもあった。
ところで、このラ・パス(La
Paz)だが、猛将フリアン・アパサ――ラ・プラタ副王領の豪族で、トゥパク・アマルの最も有力な同盟者であり、かつてアンドレスを戦士として鍛え上げた恩師でもある――が、数ヶ月前より、既に堅固な包囲網を敷き続けていた。
実は、ラ・パスは、封鎖すること自体は、それほど困難な場所ではない。

ラ・プラタ副王領で最たる要衝のこの町は、周囲を6千メートル級の山々で囲まれた盆地部分に築かれている。
補給や通信の動脈である最も重要な道路は、今も昔も、ラ・パスの西側の高地エル・アルトから入ってくる。
ペルー副王領からラ・プラタ副王領に通ずる幹線道路は、「太陽の門」などのプレ・インカ期の遺跡で有名なティアワナコを通り、エル・アルトで南に折れてオルーロ(Oruro)に達し、ここでオルーロとコチャバンバ(Cochabamba)への二つの道に分岐する。
つまり、ラ・パスへは、この幹線から枝が出ているだけである。
もちろん、この他にも小さな道はいくつかあるのだが、ともかくも、非常に険しい山々に囲まれたラ・パスは、主要な道さえ押さえてしまえば、町の全外周を包囲しなくても封鎖することが可能な地なのである。

4万の兵を指揮するアパサは、本陣をエル・アルト付近に据えていた。
その本陣からは、下方の盆地に、ラ・パスの町が一望に見渡せる。
封鎖に成功したアパサは、既に、ラ・パスに立て篭もるスペイン軍に、インカ側に有利な条件付きの和議か休戦かの選択を迫っていた。
しかしながら、アパサの突きつける厳しい条件――全ての武器の引き渡し、スペイン側の築いた要塞の破壊、暴政を敷いてきた代官の引き渡し、スペイン人をスペイン本国に帰還させること、税関吏その他の勅任官・大地主・有力な神父などの白人の引き渡し等――に、到底、妥協などできぬ敵軍は、激しい反撃に転じていた。
いかに豊かな財力や民への影響力を備えていた猛将アパサとはいえ、一介の豪族にすぎぬ彼の率いる軍は、兵力こそ多いながらも、さすがに皇族たるトゥパク・アマルやアンドレスたちが指揮する軍とは異なり、装備が悪く、ここでも、スペイン側の火砲の威力に押され、決定打を与えられぬままに時ばかりが流れていた。
当初、このラ・パスのスペイン軍を率いて戦っていたのは、アンドレスが奪還したソラータの代官を歴任したこともあるセグローラ中佐であった。
しかし、中佐の率いるラ・パスのスペイン軍がアパサの猛攻に押されていくさまを見て取って、精鋭の援軍を率いて駆けつけたのが、ラ・プラタ副王領のスペイン軍総指揮官イグナシオ・フロレスである。
結果、ラ・パスでの戦闘は、実質的には、アパサ軍とフロレス軍との激突という構図となっていた。

イグナシオ・フロレス――ペルー副王領で総指揮を執るアレッチェに次ぐほどの権限を有する、ラ・プラタ副王領のスペイン軍総指揮官。
副王からの信任も篤く、かつてはアウディエンシア(最高司法院)の議長まで務めたほどの文武両道の麗人である。
スペイン本国出身の白人たちが植民地支配の重職を牛耳る中、このフロレスは、唯一、南米出身でありながらも実力で這い上がり、今では、スペイン本国出身の重役人たちを睥睨するほどの高位についていた。
しかし、彼は、決して他者を蹴落とすことに邁進してきたのではない。
フロレスは、当時のスペイン役人には極めて珍しく、人種的差別や偏見の少ない公明正大な人柄の持ち主でもあった。
同じスペイン人でありながら、ただ植民地生まれであるという理由だけで、スペイン本国出身者から不当な差別を受け続けてきた分、それを己の毒としてではなく、むしろ糧として、より成熟した人格形成の血肉としてきたと言えようか。
いずれにしろ、さすがに装備も万全で武勇も頭脳も冴えている敏腕フロレスと彼の精鋭軍団に、一時は優勢だったアパサ軍も苦戦を強いられ、次第にインカ側の雲行きは怪しくなっていた。
ソラータから駆けつけたアンドレス率いる援軍が、当地ラ・パスに到着したのは、そのような戦況の真っ只中の頃であった。
フロレス軍の激烈な火砲にも怯まず、正々堂々と正面から、アパサ軍の盾となるがごとくに戦線に突入してきたアンドレス軍を前にして、フロレスは、苦い笑みを浮かべた。
(アンドレス、そなたと直接に対峙するのは、そなたが当副王領に来たばかりの頃…――あのプノ戦以来、二度目になる。
まさか、そなたが、ソラータを落とすまでの指揮官になろうとは)

ブロンドがかった肩ほどの長髪に、吸い込まれるような蒼い瞳を持つ優美な風貌のフロレスは、スペイン人というより、むしろ、イギリス人かフランス人のように見える。
銃よりもサーベルを好んで手にし、艶やかな白馬に凛然と跨るその姿は、相変わらず、中世の騎士さながらであった。
(アンドレス、そなたが仮にこのまま首尾よくラ・パスまでをも奪還した暁には、いよいよペルー副王領へと舞い戻る算段であろう。
そして、トゥパク・アマルと合流か……。
トゥパク・アマル――アレッチェ殿の内々の通告によれば、クスコの牢を脱して、未だ行方知れずのままだとか。
一時は処刑寸前とまで言われたあの者が、再び民衆の前に姿を現すことともなれば、インカ軍の士気は一気に高まることとなろう。
この反乱の行方、いよいよ分からなくなってきたか…――)
眼下の盆地で、勇ましく自軍に挑んでいるアンドレス軍を見下ろしながら、フロレスは、その秀麗な目元を細めた。
(それに、あのトゥパク・アマルのことだ。
牢を抜けたともなれば、裏で、いかなる策を進めているやも分からぬ。
とはいえ、スペイン側とて、トゥパク・アマルの脱獄に、ただ舌を巻いていたわけではない。
ペルー副王領では、トゥパク・アマルが姿を消して以来、今も、あのアレッチェ殿は過剰なほどに武器の増産に躍起になっている。
その勢いたるや、異常なほどに凄まじい。
倍加された火砲の威力に、そなたたちインカ軍が、果たして、どれほど太刀打ちできるのか……)

一方、指揮官となった現在も、以前と変わらず、自ら最前線に立って味方の軍団を鼓舞しながら戦うアンドレス――彼も、また、上方に構えられたフロレスの本営を、鋭い横顔で決然と見上げていた。
突き刺すような真冬の冷風が、敵の刃のごとく全身に吹きつけてくる。
(フロレス殿!!
あなたと、また、こうして戦う日が来ると思っていました!!
あのプノ戦で有耶無耶になった勝敗の決着、今度こそ、つけさせて頂く!!
この戦い、何が何でも、負けられない!!
再びトゥパク・アマル様のおられるペルー副王領に戻り、そして、今度こそ、インカの真の勝利を掴み取るために――!!)

こうしてラ・パスでの戦闘は、真冬にもかかわらず、熱く、激しく、燃え上がっていったが、それでも、夜間は、両軍は共に刃を収め、静かに、その痛めた翼を休めた。
日中の激戦の壮絶さが嘘のように静まりかえった眼下の戦場を、高台の野営場から見下ろすアンドレスの傍に、アパサがチチャ酒の入った大瓶と木のカップを二つ持って現われた。
そして、そのまま、雪の結晶で覆われた草の上に、ドッカと、腰を下ろす。
アンドレスが振り向くと、アパサは、早速、地面に置いた両方のカップに並々と酒を注(つ)いでいる。
無防備なほどにリラックスしきった態度で、しかも、酒まで持ち出してきたアパサの様子に、驚いたような目をしているアンドレスを一瞥すると、アパサは面白そうに片目で笑う。
それから、アンドレスの腰にさげたサーベルに、ちらりと横目を走らせた。
「どうだ?
そのサーベル、少しは役に立っているか?」
「あ…!
はい!!
それは、もちろん!!」
アンドレスは素早く腰に手をやると、鞘(さや)の上から、ギュッと、重厚なサーベルを握り締めた。
使い込まれていくほどに、限りなく霊妙な気と力を高めていくかのような、そのサーベルは、今、目の前にいる恩師アパサ譲りのものだった。

スペイン人の厳重な監視下におかれた神学校を卒業したての頃、何も知らなかったアンドレスに、アパサは、剣技から戦術指南まで、全てを基礎の基礎から徹底的に叩き込んだ。
このアパサは、反乱計画の初期段階からトゥパク・アマルの最も有力な同盟者の一人であり、その腕を見込まれ、トゥパク・アマルからの強い願いに押されて、アンドレスの武術指導を引き受けたのだった。
数年間に渡る鬼のように厳しく容赦の無いアパサの指導に、心身共にズタズタになりながらも、懸命に特訓に励み続けたあの日々。
それほど昔のことではないはずなのに、あれから、とても、とても、長い時が流れたかのように思える……。
そして、全ての特訓が終わった最後の日、アパサは、大事にしていた己のサーベルを、アンドレスに譲り渡したのだった――。
不意に、アンドレスの脳裏に、あの日の一場面が甦る。

『それを、おまえにやる。
持っていけ』
揺れる眼差しでアパサを見上げるアンドレスの瞳の中で、アパサは静かに笑っていた。
『おまえはよくやった』
サーベルを掲げ持ったまま、アンドレスは深く頭を下げた。
『本当に、何と御礼を申し上げたらよいのか…!』
思わず涙が込み上げそうになるのを、彼はぐっと堪えた。
アパサは低く深遠な声音で続けた。
『これまで敵を攻撃することばかりを言ってきたが、おまえに渡したこのサーベルは、ただ攻めるだけのものではない。
そもそもサーベルとは、攻めるよりも守ることに優れた武器なのだ。
サーベルには、敵のもつ銃や大砲には無いものが宿っている。
それは、美しく、魂と呼ぶにふさわしい雰囲気とも言えるだろう。
おまえには合っている』
アンドレスは、あの日を懐かしく思い返しながら、既に酒を仰ぐように飲んでいるアパサの傍に身を屈めて、深く礼を払った。
「アパサ殿に戴いたこの剣!
今では、俺の分身も同然です!!」
「ふ…」
アパサは酒をあおりながら、横目でニヤリとする。
「アンドレス、おまえ、何を生意気な。
分身だと?
そんな大口たたくのは、10年は早いだろうがっ!
つい、こないだまで、剣の持ち方ひとつ、いや、立ち方ひとつ知らなかったくせに」
「…!」
赤面しているアンドレスの方を、相変わらず、せせら笑うように目の端で見ながら、意地悪な声音でアパサは続ける。
「ほれ!
そうやって、すぐ顔に出るところも、ちっとも変わっちゃいない」
「――!!」
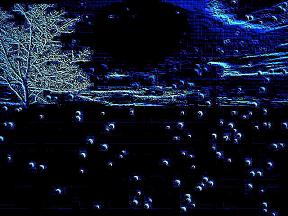
「アンドレス、おまえ、よく、それで大軍の将なぞ務まっているな。
俺には、全く、信じられんよ」
アパサの一言一句に、憤然と顔を火照らせながら、やがて、アンドレスは切り返すように、キッと、アパサを睨んだ。
「アパサ殿だって、あの頃と全然変わっちゃいないじゃないですか!!
こんな戦場でまで、酒なんか飲んで!!
敵が夜襲でもかけてきたら、どうするんです?!」
「ふふん。
そうやって、すぐ、人の言葉に感情を煽られるところも、変わらねぇしなぁ」
アパサは鼻で息を吐くと、いかにも上手そうにグビグビ喉を鳴らして酒を飲み干した。
そして、口の周りを荒々しく腕で拭いながら、冷ややかな視線をアンドレスに投げる。
「余計な心配なぞ、するな。
あのフロレスは、夜間の奇襲など、絶対にかけてこない」
「え…!
絶対?!」
「しっ!
声がでかい。
少しは落ち着いて座れ。
それから、その酒!
おまえの分だ」
憮然と戸惑いの入り混じった面持ちで、差し出されたカップを受け取りながら、アンドレスはアパサの脇の地面に座った。
降り積もった雪の冷たさが、腰からヒヤリと身に染みてくる。
「それじゃ、敵は、絶対に、夜襲をかけてこないってことですか?」
「そうだ。
だから、俺も、夜の奇襲はかけない」
アンドレスは、「え!」と、さらに目を見開いた。
「そのような状況なら、それこそアパサ殿なら、敵の油断をついて夜襲をかけそうなものかと…!!」
そんなアンドレスを、アパサは、いっそう冷ややかに横目で一瞥した。
彼は新たに注いだチチャ酒をすすりながら、やや真面目な口調になって言う。
「アンドレス。
この反乱で、白人どもの汚いやり口ばかり見せられて、おまえ自身までが、泥に染まってしまったのか」
「!!」
アンドレスは、カップを両手で握り締めたまま、ますます顔を紅潮させた。
「だっ…だって、アパサ殿ではないですか!
昔、俺に戦術指南をしてくれた時、ズルくなれって言ったのは」
「ふん…!
あれは、相手が、姑息(こそく)な奴の場合だ」
「…――!」

「もともと昔からインカの戦(いくさ)のやり方は、そんなズル臭いやり方なんかしなかった。
何せ、田畑を耕しながら、その合間に戦をしていたんだからな。
今のように大地を荒らしたままでの戦など、200年前までのインカ時代では、考えられぬことだった。
まず、耕す。
そして、互いに休む時は、休む。
戦をするんなら、大地が許してくれる隙間だけにした。
だから、当然、休むべき夜間に、決して攻めてこない相手なら、こっちからも攻めはしない。
ふふん…あのフロレスは、そういう戦い方のできる男なのだ。
白人にしておくのは、勿体無いほどだ」
アパサは早々にカップを飲み干すと、再び空いたカップに、溢れる程なみなみと酒を注いだ。
それから、今度は、口の端に笑みを浮かべて言う。
「おまえも飲め。
ソラータを奪還した祝杯だ!」
アンドレスは、まだ頬を上気させたままアパサに礼を払って、やっとチチャ酒を口元に運ぶ。
高地の冬は、雪混じりの冷たい強風が吹きつけ、二人の羽織った分厚いポンチョの裾を容赦無く翻して去っていく。
冷え切った体を温めようとするかのように、酒を飲み急ぐアンドレスに、酒瓶を差し出しながら、アパサがポツリと言う。
「トゥパク・アマルの…――」
「え…?!」
トゥパク・アマルの名に、アンドレスは反射的に振り向き、その彫像のようなクッキリとした目を見開いて、じっとアパサを見つめた。
そんなアンドレスを、アパサは手で払うようにして言う。
「やめろ!
そう、目をでかく開けて、こっちを凝視するな!
怖いぞ…!」
「怖ッ…?!」
アンドレスは、ついに不貞腐れた顔で横を向いた。
それでも、アパサの言葉の先を促す。
「そ…それで、トゥパク・アマル様が……?」
「うむ…。
おまえのところにも、使者が行ったろう?」

アンドレスは、ハッと顔を上げた。
「では、アパサ殿も、ご存知ですか?!
トゥパク・アマル様の脱獄のこと…!!」
「シッ!!
声がでかい」
アパサは険しい眼で、アンドレスを睨んだ。
アンドレスは身を縮めて、咄嗟に己の口を押さえる。
「ったく、アンドレス、おまえなぁ…!
今は、相手があのフロレスだから良かったが、違ったら、その辺の草むらに、敵方の斥候がウヨウヨだぞ。
そんな大声だしたら、敵に何もかも筒抜けだろうが」
「すいません…!」
アンドレスは、まだ口を押さえたまま、さらに身を竦(すく)めた。
そんなアンドレスを眺めやりながら、アパサは声を低める。
「俺も驚いたが、あの書状は、間違いなくトゥパク・アマルの筆跡だった。
妻子まで連れて脱獄だなんて、無茶な真似を……!
おまえにもそうだが、昔から、あいつには、ヤキモキさせられることばっかりだ」
そう言いつつも、大きく瞳を輝かせるアパサの野性的で精悍な面差しには、強い恍惚が滲んでいる。
そのアパサの横顔に、アンドレスの胸は、ぐっと熱くなった。
このアパサが、トゥパク・アマルの捕縛をどれほど悔やみ、案じ、救出できぬ無力感に苛まれてきたか――決して表には出さなくとも、つきあいの長いアンドレスには痛いほど分かっていた。
「アパサ殿……!」
感極まった瞳で、真っ直ぐに己を見つめるアンドレスの視線を、再び、払いのけるようにしながら、今度はアパサが顔を赤らめ、鬱陶しそうに立ち上がった。
「だからっ、そういう目で見るなって!!」
そんなアパサの一挙一動から、トゥパク・アマルが無事と知って心底嬉しいのだと、そのアパサの思いが溢れるほどに伝わってきて、アンドレスは、感動と微笑ましいのとで、思わず顔をほころばせた。
「ふ…ぷっ」
「!……アンドレス、おまえ!!
何が可笑しい!!」
「いえ…プッ!」
「!!!―――」
照れなのか怒りなのか、アパサは顔を真っ赤にすると、グルリと方向を変え、「あー!!メシ、メシっ!!」と、がなりながら大股で去っていく。
そんな恩師の後ろ姿を止まらぬ笑みを零しながら見送りつつ、アンドレス自身も、トゥパク・アマルのことを思って、また感動を噛み締める。

彼は立ち上がり、幾重にも連なる霊峰を隔てた先にある、遥かなるペルー副王領の方角を振り仰いだ。
(トゥパク・アマル様――!!
ああ……はやく…はやく、お会いしたい!!)
こうして、平穏な夜のひと時は過ぎ、日が昇れば、再び、両軍の戦闘は幕を開ける。
ラ・パスのインカ軍とフロレス軍は、激戦を交えながらも、互いにとどめを刺せぬままに、時は流れていった。
インカ側は、ただでさえ兵力に優れるアパサ軍に、装備のよいアンドレス軍が合流したことで、今やフロレス軍を圧倒するほどの強力な大軍となっていた。
とはいえども、さすがに副王直属のスペイン王党軍たるフロレス軍の火砲の威力は凄まじく、また、指揮官フロレスの元、その砲撃力も非常に良く訓練されており――いずれにしろ、互いの力は拮抗し合い、両軍は完全に互角なままにいた。
そして、そうした戦闘の続く日々の中、ある晩、アンドレスは夢を見た。
最初に目に飛び込んだのは、紺碧に輝く鏡のような湖。

(え…?
あれは、ティティカカ湖……?!)
ティティカカ湖――インカの創造主ビラコチャ神が降臨したと言い伝えられる神秘の古代湖。
そして、その沿岸に広がる乾いた平原――…。
それは見覚えのある戦場の光景だった。
激しい戦闘の展開する戦場の一角で、何者かを前にして、サーベルを握る自分が見える……対峙する相手は――……?
アンドレスは、夢の中で、朦朧としつつも、懸命に意識を彷徨わせた。
湖から吹きつける風に舞う金色の長髪、そして、深遠な湖のごとく透明な蒼い瞳――その眼差しは、鋭くも、極めて沈着な気配を湛えている。
アンドレスは、ハッと息を詰めた。
(フロレス…――!!)
それは、かつてのプノ戦の一場面だった。
(あの時と…何もかも、あの時と同じ……!)
夢の中で、アンドレスは、かのプノ戦に臨んでいた時と全く同じ状況下にある己の姿を、凝視した。
ティティカカ湖畔に広がるプノの戦場にいる自分は、あの時と同じように、唇を引き結び、焔の燃え立つような激しい眼で、騎馬のままサーベルを構えている。
対する相手は、あの敵将フロレス―――!!
『フロレス殿!!
ここで会ったが、互いの運命!!
お命、頂戴いたす!!』
汗ではりついた前髪からのぞく、炯々たる漆黒の瞳は、もはや完全に獲物を狙う武人のそれであり、否、それ以上に、今は獰猛な気配さえ湛えている。

一方、眼前のフロレスは、まさに、あのプノ戦の時と同様、白馬に跨り、研ぎ澄まされた優美な動作で、ゆっくり、完全に隙無く、サーベルを構えゆく。
そして、その美麗な目元を、僅かに細めた。
彼のサーベルの先端が、陽光を受けて、滑らかな閃光を放つ。
アンドレスとフロレスは互いを睨み据えたまま、片手にサーベル、そして、片手に愛馬の手綱を手繰りながら、己に有利な間合いを掴むため、小刻みな移動を繰り返す。
双方共に全く隙が無く、なかなか容易に切り込むことができない。
二人の険しい視線のみが、無言のままに絡み合う。
そのまま、どれほどの時が経過しただろうか。
傍(はた)から見れば、単に、間合いを取り合っているだけの単純な動作である。
しかし、熟達した剣士である二人には、それだけで、双方の力を見抜くに充分であった。
しかも、今のアンドレスには、これは夢だと、あのプノ戦の時と全く同じ情景を繰り返しているだけなのだと、どこかで分かりながらも、その意識は、まるでブラックホールに吸い込まれていくがごとくに、あの時の状況に、身も心も無抵抗に呑み込まれていく。
(ああ…これは、夢だ…!
夢なのに……!!)
…――やがて、それが夢か現(うつつ)かも定かではなくなり、彼の意識は、完全に、その戦場の場面へと舞い戻っていた。
剣を握る手の平に、確かな発汗さえ覚える。
己の目の前で、馬の手綱を手繰りながら間合いを計り続けるフロレスの動きは、舞うように優美でありながらも、完璧に隙が無い。
その鍛錬され抜かれた相手の動きと、同様に研磨され抜かれた相手の全身に、アンドレスは睨むような険しい視線を走らせた。
(くっ…!
フロレス…こいつ……!)
きつく唇を噛み締めながらも、彼の全身には、師たるアパサと対決した時にさえ覚えたことのない手応えに、ゾクゾクと鳥肌が立たずにはいられない。
互いの喉元を、心臓を、腹部を――血に飢えた魔物のごとく狙い定めて微動する剣先に、真昼の陽光が滑(ぬめ)るように反射する。
さして動いているわけでもないのに、恍惚の滲んだアンドレスの鋭い横顔には、既に幾筋もの汗が伝っていた。
果たして、戦場の二人は、どれほどの間、間合いを計り続けただろうか。
互いに、切り込む隙を全く掴むことができない。
しかし、ついに、二人はピタリと動きを止めた。
アンドレスの全身から、瞬間、焔のごとくオーラが燃え上がる。
(フロレス!!
覚悟――!!)
先に勝負を仕掛けたのは、アンドレスの方だった。
彼は、決然たる剣裁きで、フロレスへと一直線に切り込んだ。
彼の全身が、唸る風を切って相手に迫る。

だが、フロレスは、完全に動きを止めたまま、微動だにしていない。
騎乗の彼は、猛然と迫り来る相手を見据えながら、その安定した構えを一縷(いちる)も崩すことなく、眉一筋さえ身じろぐこともないままに、そこにいる。
アンドレスはサーベルを水平に握り締め、一気にフロレスとの距離を詰めた。
ついに互いの体が交差する瞬間、アンドレスは、水平に構えていた己のサーベルを、フロレスの喉元へと光の矢のごとく突き出した。
一方、その最後の最後まで、フロレスは全く動かない。
陽(ひ)に透けるブロンドの髪だけが、風の中に舞い上がる。
そのままアンドレスのサーベルは、確実にフロレスの首を貫くはずであった。
―――が、手応えが無い!!
己の意識よりも早く、アンドレスの鍛えられた動体視力は、フロレスが、首の一捻りで己のサーベルを避けるのを、はっきりととらえていた。
『!!』
アンドレスは、衝撃よりも、むしろ、強い恍惚に瞳を輝かせて息を呑む。
(なんという冷静さ!!
フロレス、この者は…――!!)
だが、その一瞬の隙を狙うようにして、今度はフロレスのサーベルがアンドレスの喉元に襲い掛かる。
しかし、実戦の中で無数の銃弾をかわしながら、図らずも心眼を研ぎ澄ませ続けてきたアンドレスは、この時も反射的にその剣先をかわした。
彼は馬上で敏捷に体勢を立て直すと、再び、疾風のように切り込んでいく。
サーベルの描く蒼い軌跡が、宙に光の筋を引いて走る。
だが、フロレスのサーベルも、また、アンドレスの剣先を確実に受け留め、俊敏に切り返す。
二人のサーベルが交わる鋭い金属音が、幾度も戦場に鳴り響いた。

それでも一瞬も止まることなく、アンドレスのサーベルは、繰り返しフロレスを狙った。
それをフロレスが弾き返す。
そして、また両者は素早く間合いを取る。
二人の目が光った次の瞬間には、蒼い残光と共に正面から互いが交差する…――!!
天空まで響き渡る剣と剣の交わる鋭い金属音―――!!

その瞬間、アンドレスは、ハッと目を覚ました。
「!!!」
広がる漆黒の闇……そこは、ラ・パスの陣営の己の天幕の中だった。
あまりに夢に没入してしまっていたためか、それが夢だったのだと、状況を把握するまでに暫くの時間がかかった。
アンドレスは、バッと、寝台から身を起こす。
そして、先ほどまで剣を握っていたはずの手を、暗闇の中で呆然と見下ろした。
「あ…!」
手の中に、びっしりと汗が噴き出している。
その間にも、大きく肩が前後し、まるで本当に戦っていたかのように、すっかり息が上がっていた。
(や…やっぱり…夢……!
しかも、あのプノ戦の時と全く同じ場面…――)
アンドレスは、静寂な深夜の闇を見つめた。
(フロレス……)
その彼の耳元に、先日のアパサの声が甦る。
『心配するな。
あのフロレスは、夜間の奇襲など、絶対にかけてこない』
『え…!
絶対?』
『今のように大地を荒らしたままでの戦など、200年前までのインカ時代では、考えられぬことだった。
まず、耕す、そして、互いに休む時は、休む。
戦をするんなら、大地が許してくれる隙間だけにした。
だから、当然、休むべき夜間に、決して、攻めてこない相手なら、こっちからも攻めはしない。
ふふん…あのフロレスは、そういう戦い方のできる男なのだ。
白人にしておくのは、勿体無いほどだ』
アンドレスは寝台に座り込んだまま、鋭い目で、濃い闇を見据え続ける。
(あんな戦い方をする…あの男―――!
スペイン人なのに……!
一体、どんなやつなんだ…?)


